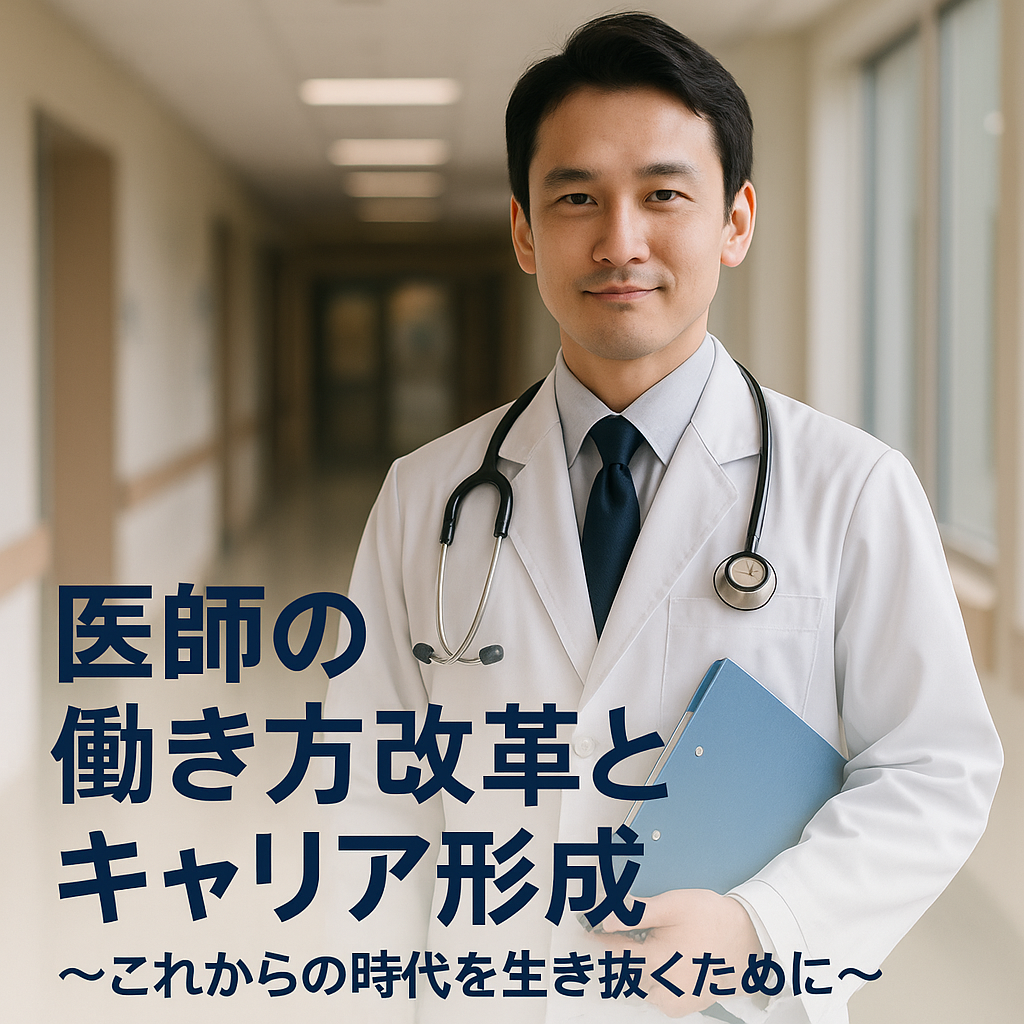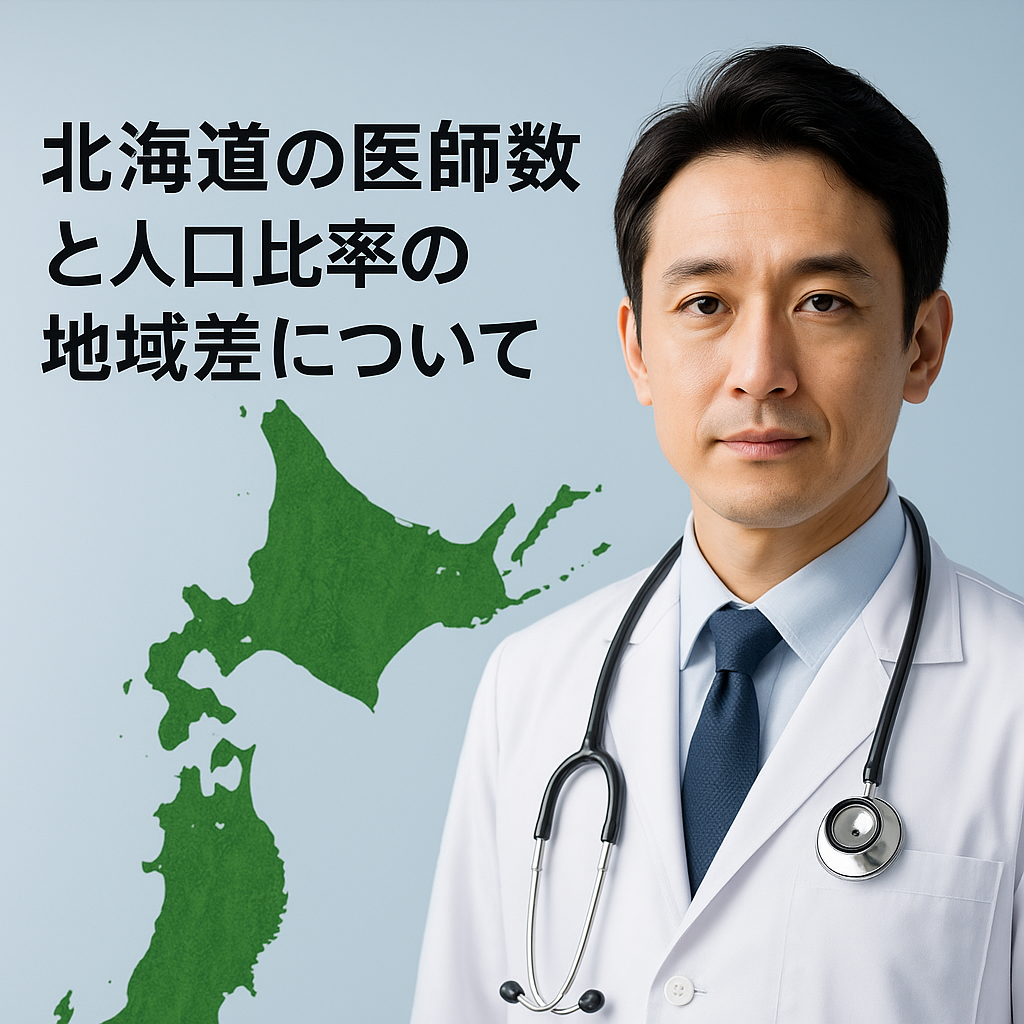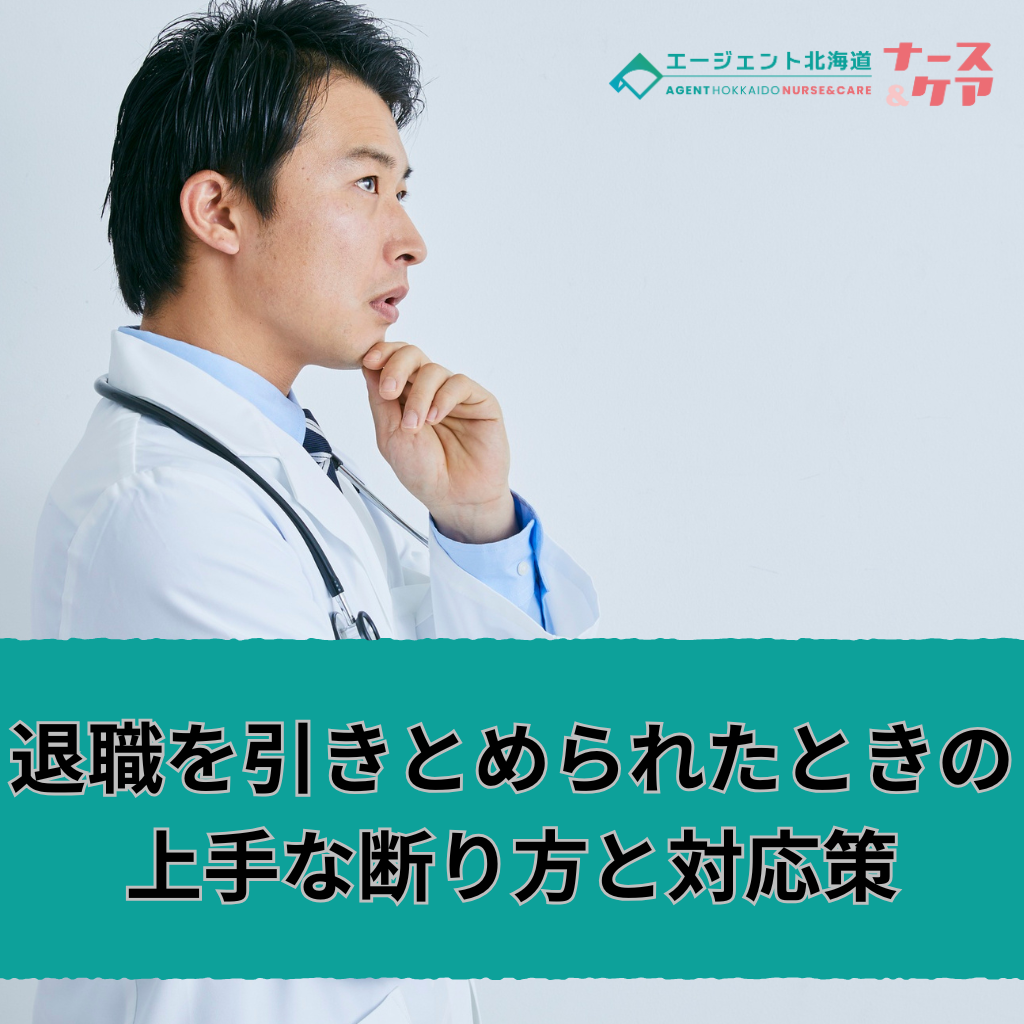近年、医療業界でも「働き方改革」が進められており、2024年4月からは医師にも時間外労働の上限規制が適用されるなど、大きな変化の波が押し寄せています。これまで過酷な労働環境が当たり前とされてきた医師という職業において、「働き方」を見直すことは、一人ひとりのキャリア設計にも大きな影響を与えます。
本記事では、医師の皆さんが知っておきたい働き方改革のポイントと、それを踏まえたキャリアの考え方についてご紹介します。
もくじ
1. 働き方改革の背景と目的
働き方改革は、単に「労働時間を短くする」ことが目的ではありません。医療現場における長時間労働や過労死リスクを軽減し、持続可能な医療提供体制を築くための取り組みです。
これまで、医師は365日24時間体制での勤務が求められ、月100時間を超える時間外労働が常態化している施設も珍しくありませんでした。そうした状況に対して、医療の質を担保しつつ、医師の健康や生活の質(QOL)を守るための改革が必要とされてきたのです。
2. 医師の時間外労働規制とは?
2024年4月より、医師にも労働基準法に基づいた時間外労働の上限が適用されました。主なポイントは以下の通りです。
A水準(原則としてすべての勤務医に適用)
- 年間時間外労働時間の上限は 960時間
- 月あたりの上限は 100時間未満
B水準(地域医療確保暫定特例水準の医師)
- 年間で最大 1860時間 まで可能(条件付き)
- 連携B(医師を派遣する病院) 1860時間
- 各院では960時間
C-1(臨床・専門研修) C-2(高度技能の修得研修)
- 年間で最大 1860時間 まで可能(条件付き)
この規制により、病院側も医師のシフト体制の見直しや、業務の分担、タスク・シフティングの推進が求められるようになっています。
3. 医師のキャリア形成に与える影響
働き方改革によって、医師のキャリアはどのように変わっていくのでしょうか?いくつかの側面から見てみましょう。
- 「働き方の選択肢」が増える時代へ
以前は「大学病院で研鑽を積む」「市中病院で常勤医として働く」という限られた選択肢が一般的でした。しかし今は、常勤・非常勤の働き方を組み合わせたり、週4日勤務や当直なしの勤務など、自身のライフスタイルに合わせた働き方を選ぶ医師が増えています。
また、オンライン診療や企業でのメディカルアドバイザー、医療ベンチャーとの協業など、病院以外で活躍の場を広げる医師も少なくありません。
- ワークライフバランスと専門性の両立
従来、専門性を高めるには長時間労働が不可欠とされていましたが、働き方改革以降は「限られた時間内でどう成果を出すか」が重視されるようになっています。
これは、教育体制やOJTのあり方、診療支援体制の見直しにもつながり、結果的に若手医師の育成環境が整うきっかけにもなりつつあります。
- キャリアの「多様性」と「再設計」が重要に
たとえば、ある程度経験を積んだ後に地方病院で地域医療に貢献する、もしくは留学や研究にチャレンジするなど、キャリアの「第二ステージ」や「再設計」を意識する医師も増えています。
このような柔軟なキャリアパスを実現するには、若いうちから「将来どのような働き方をしたいのか」「自分が大切にしたい価値観は何か」を見つめ直すことが重要です。
4. 医師のキャリア形成に役立つアクション
① 定期的な自己棚卸を行う
年齢やライフステージによって、理想の働き方や価値観は変化します。少なくとも年に1回は、自身の働き方やキャリアについて振り返る時間を持ちましょう。
② キャリア相談を活用する
人材紹介会社やキャリアコンサルタントは、医師のキャリア設計において非常に心強い存在です。第三者の視点からアドバイスを受けることで、視野が広がり、自分では気づけなかった選択肢に出会える可能性もあります。
③ 情報収集とネットワークの構築
医療系の勉強会やカンファレンス、オンラインセミナーなどを活用し、最新の医療情報だけでなく、他の医師のキャリア観に触れることも重要です。同じ志を持つ仲間とのつながりは、将来的に大きな財産になります。
5. 最後に:医師としての「自分らしさ」を大切に
働き方改革によって、医師という職業の常識が変わりつつありますが、それは「自由度が増した」という捉え方もできます。医師一人ひとりが、自分らしいキャリアを築くためのチャンスと捉え、情報にアンテナを張りながら柔軟に動いていくことがこれからの時代に求められます。
忙しい日々の中でも、ふと立ち止まって「自分は何のために医師をしているのか?」を見つめ直す時間を大切にしてください。